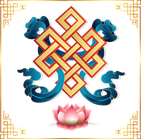禅とは何か
「禅」の起源については、インドから中央アジアにかけて興隆した大乗仏教が中国に到達し、老荘の無為自然思想と融合して成立したと考えるのが一般である。しかし私は、南インドの達磨の西来によって釈尊直説(人間ブッダの教え)が原型のまま中国にもたらされたのが「禅」であり、すなわち「禅」とは釈尊直説そのものである、と考えている。
現に、最古の仏教経典とされる「スッタ・ニパータ」の中でも特に最古層とされる第4章・第5章の中には、
「眼を下に向けて、うろつき廻ることなく、瞑想に専念して、大いにめざめておれ。心を平静にして、精神の安定を保ち、思いわずらいと欲のねがいと悔恨とを断ち切れ。」(972)
という一文がある。その内容から釈尊直説(人間ブッダの教え)であると考えられる。釈尊が生きた時代には、当然ながら礼拝対象も経典もなく、修行の方法としては瞑想しかなかった(なお、托鉢は修行するために食を得る手段に過ぎず、修行そのものではない)。釈尊自身、苦行を捨て、菩提樹の下で7日間の瞑想の末に悟りを開いたとされており、ここに禅の源流があるとみて間違いないであろう。
インド・ガンジス川中流域に始まる釈尊の教えは、入滅後100年ころ(マウリヤ朝時代)の部派仏教団内部での上座部と大衆部の根本分裂を経て、大衆部系の一派がインド北西部(現在のパキスタン)のガンダーラ地方でヘレニズム文明と出会い、舎利塔・法輪信仰から仏像・菩薩崇拝へと変貌を遂げた。その後、イラン系のクシャーナ朝の庇護を受け、ゾロアスター(拝火)教の影響などもあって大衆化された結果、中央アジアを中心に大乗仏教として隆盛を迎えた。
その後のグプタ朝時代では、釈尊の教えはバラモン教に先祖返りした密教として神秘化し、そのまま土着のヒンズー教へと吸収され、さらにイスラム勢力の侵攻を受けてほぼ消滅した。しかし、その前に中央アジアに脱出していた大乗仏教が、経典作者の手による「文字」として、三蔵法師たちによってシルクロードを通って中国へ、そして飛鳥時代の日本へと伝えられたのである。これが禅宗以外の「経典仏教」の日本への伝来ルートである。この北伝仏教では内容に様々な創作が加えられ、各経由地の土着思想と融合した結果、釈尊直説とはかけ離れているどころか、釈尊直説では禁じられていた偶像崇拝や呪文・占術、バラモン教(ウパニシャッド哲学)の教義である輪廻転生などが仏教の範疇に含まれるようになった。有名な「般若心経」もその後半部分は呪文で構成されている。釈尊は、後の世に自らが超能力者に祭り上げられたり、加持祈祷やおみくじが仏教の名の下に行われるようになるとは、思いもよらなかったであろう。
このような「創作仏教」である大乗仏教の中国・日本への伝播とは別に、小乗仏教団の上座部系の一部がマウリヤ朝時代に釈尊直説(人間ブッダの教え)を比較的保ったままスリランカに伝わり、その後海のシルクロードである季節風貿易ルートを通って東南アジアに南伝した。さらに後世になって、5世紀の南インドに生まれた達磨により、経典によらない「不立文字」としての釈尊直説、つまり釈尊が生きた時代の純粋な仏教が海路中国へ、そして時代が下り道元によって鎌倉時代の日本へと伝えられたのである。これが禅の正伝ルートである。達磨も道元も、一巻の経典も携えずにその身一つで釈尊以来の正伝の仏法を異国から伝えた(教外別伝)。この二人は、それまでの仏教の大衆化・神秘化に抗して人間ブッダの教えへの回帰を唱えた「仏教原理主義者」であったといえる。そもそも釈尊直説には輪廻転生など独立不変の実体(アートマン)を前提とするバラモン教(ウパニシャッド哲学)の教義は含まれておらず、その粋である禅においても同様である。
なお、達磨が中国に伝えたのは大乗仏教であるという主張もあるが、達磨は密教が盛んになったグプタ朝時代に南インドの香至国(現在のチェンナイ付近)に生まれたとされており、むしろ仏教がバラモン教に先祖返りして神秘化し、ヒンドゥー教に取り込まれて大衆化していた時代である。達磨は、釈尊入滅後1000年近くが経って釈尊直説(人間ブッダの教え)とはかけ離れたものとなっていた当時の仏教を憂え、師である菩提多羅から受け継いだ正伝の仏法を中国に伝えるために西来を決意したのであり、そのようにして達磨が伝えた本来の禅が、既に中国に伝わっていた大乗仏教と融合して中国禅となったと考えるべきであろう。
禅の特色は、教え自体は不立文字・教外別伝・以心伝心といいながらも、古来、中国で多くの指南書(語録)や問答集(公案集)が編纂されたことである。禅問答といえば、一般的には訳の分からないやりとりの代名詞とされるが、只管打坐を専らとする曹洞禅ではあまり用いないものの、公案を併用する臨済禅では、「参禅」という師匠と弟子が1対1で対峙する場で、自らの「仏性(自分の正体)」に気付かせ、悟りに導くために真剣勝負の問答が行われる。世俗的な思考の限界を超えるところまで徹底的に思考させる、一種の逆療法である。
その一つのパターンは、弟子から「如何是〇〇」(いかなるか、これ〇〇)と問われ、師匠が何の変哲もない日常のものを挙げる、というものである。例えば、
弟「如何なるか、是れ仏?」(仏とは何でしょうか?)
師「麻三斤(まさんぎん)。」(三斤の重さの、あさである。)
弟「如何なるか是れ道?」(仏道とは何でしょうか?)
師「平常心是道(びょうじょうしんこれどう)。」(普段どおりの心である。)
師「如何なるか、是れ祖師西来意(そしせいらいい)?」(達磨大師が西のインドから中国にやって来た意味(仏法の極意)とは何でしょうか?)
師「庭前柏樹子(ていぜんはくじゅし)。」(庭に生えているカシの木である。)
など。
いずれの師匠の答えも今では禅語として有名であるが、これらのもの自体に特別な意味があるわけではない。答えは何でもいいのである。要するに、仏性(自分の正体)とは、特別なものでも隠されているものでもなく、生きとし生けるものや日常の事物一切に、すべて包み隠さず現われている、ということである(一切衆生悉有仏性)。
別のパターンに、師匠が「〇〇はどこへ行った?」などと問い、それを自分とは別物として答えた弟子にお仕置きをして仏性(自分の正体)に気付かせようとする、というものもある。問題となっているのは常に己事究明(自分の正体は何か)ということであり、自分自身に置き換えなければ答えにはならない。例えば、
師「(飛んで行った鳥を見て)あれは何だ?」
弟「野鴨です。」
師「その鴨はどこへ行った?」
弟「向こうへ飛んでいきました。」
師「ここにいるじゃないか!(と言って弟子の鼻をひねり上げる)」
弟(痛さのあまり、ハッと気づく)
という有名なやりとりがあるが、自分と野鴨の間に境界線を引いて別物であることを前提に「向こうへ飛んで行った」と答えた弟子に対し、仏性の現れである点で自分と野鴨の区別自体がなく、見たまま感じたままの意識現象しかないことを、痛覚をもって悟らせようとしたわけである。
我が身はもとより、他人も動物も、麻もカシの木も、山川草木すべてが仏性の現れであり、もとより境界はない(自他一如、主客同事)という世界把握、すなわち仏教でいう「無分別智」に至ることが悟りであり、その境地に導くために公案があるのである。
自分(主体)と自分以外(客体)が別個独立に存在し、主体が客体を認識しているという世間の常識(分別智)からは到底理解できない話である。しかし、自分と環境の間に境界はなく、そこには見たまま、感じたままの意識現象があるだけで、その意味では我が身を含む全世界が「同事」であるという無分別の境地に立てば、公案の禅問答は容易に理解できる。すなわち、意識現象とは別に外界がある(私が外界を認識している)という世界把握ではなく、確実なものは意識現象しか存在しないという世界把握によれば、自分と環境の区別自体がないのであるから、すべては環境であると言ってもよいし(山を見れば自分が山になり、花を見れば自分が花になる、の無我の境地)、逆にすべてが自分であると言ってもよいのである(山も花も自分である、の唯我の境地)。無我とは、我が全く無いという意味ではなく、我と我以外との「境界」が無い(=無限)という意味なのである。
そうすると、次の有名な公案のやりとりは、どのように解釈できるか?
弟「如何なるか是れ奇特の事?」(素晴らしいこととは何でしょうか?)
師「独坐大雄峰(どくざだいおうほう)。」(この山で一人で坐禅していることである。)
弟(師匠に対し礼拝する)
師(弟子に対し鞭ち打つ)
師匠の答えを受けて礼拝した弟子を鞭で打ったということは、師匠の答えは弟子を試すためのカマかけであり、真意ではないと解すべきであろう。すなわち、そもそも仏性の観点からすれば、奇特な(素晴らしい)事と奇特でない事の区別自体がないのであり、あたかも孤高の坐禅修行が素晴らしいことであるかのように言う師匠のカマかけにハマって納得した様子の弟子を見て、いまだ独善的な分別智の世界にいて悟りには程遠いことを叱咤したということであろう。有名な「日日是好日」の公案も同じ趣旨である。毎日が好い日なら、悪い日がないだけでなく、好い日もないことになる。自分が好い悪いを勝手に決めているだけのことである。
これも有名な、中国禅宗六祖慧能(えのう)にまつわる公案である。
(ある禅寺の前で、風に揺れる旗を見て、二人の僧が言い争っている)
「あれは風が動いているのだ!」
「何をいうか、あれは旗が動いているのだ!」
(そこへ通りかかった六祖いわく)
「風でも旗でもない、あなたがたの心が揺れ動いているのだ」
公案では「風でも旗でも心でもない。六祖の真意は何か?」という問いになっている。禅においては意識現象しか存在しない以上、現前する「見えたまま、感じたまま」以外に真実はない。あたかもその背後に真実が隠れているかのごとく、動いているのは風だ、旗だ、心だなどと頭で考えた「分析」や「識別」=分別を加えている時点で、既に迷っているということである。
その意味では、いわゆる地動説と天動説も同じである。禅における真実は「見えたまま、感じたまま」しかないから、東から上ったお日様が西に沈むというだけのことである。地球が回っているのを地上で見た人はいないであろう。禅の世界では、地動説など虚妄の論ということになる。かといって天動説が正しいというわけでもない。思考をもって「○○説」と分析した時点で既に真実とはかけ離れているからである。理論化した時点で既に間違いであり、禅には「真実」はあっても「真理」はないのである。西から上ったお日様が東に沈んだとしても、そう見えたのなら、それでいいのだ。へんかいかつてかくさず、すべての真実は現前している。
科学的には、山に反射した光=電磁波が網膜を刺激して視神経から脳に電気信号が伝わって山が見えるとか、雨粒が周りの空気を振動させて鼓膜を刺激して雨音が聞こえるといった説明がなされる。しかし、真相は逆である。現に緑の山が見えており、雨音が聞こえているという意識現象があるからこそ、そのような山があり雨が降っていると「推測」しているに過ぎない。リンゴが落ちるのも万有引力があるからではない。リンゴが落ちたという事実から万有引力の法則があると「推測」しているに過ぎない。科学的真理はあくまで仮説であり、意識現象そのもの以外に真実はないのである。我々が経験している背後の世界は不可知である。網膜や鼓膜や神経や脳も含め、どれだけ物質の観察や実験を重ねようとも、結局は我々の感官の知覚による意識現象を通してしか世界を把握できないからだ。ゆえに、個人(事実)あって経験があるのではなく、経験あって個人(事実)があると「推測」していることになるほかない(西田幾多郎)。
夕焼けが赤いというのも、人間の目には赤く見えるというだけの話であって、本質的に夕焼けが赤いわけではない。色というものはそれを見る生物がいて初めて意味を持ち、生命体が絶滅すればそれは何色でもないからだ。もっといえば、世界があるというのは、人間にはあると感じられるというだけの話であって、人間がいなければ世界は存在し得ない。そして、我々は自分の意識から抜け出すことは決してできない。一人一宇宙の世界からの逃げ場はないのである。これを「天上天下唯我独尊」という。
ただ意識現象のみが現実であるという「禅」は、根本的に世親の唯識思想に通ずるものがある。もっとも、唯識思想ではアラヤ識が刹那滅しながら相続されるとして輪廻転生の主体を認めるが、禅では概念の解体により徹底して自我を解体するので認めない。その意味ではむしろ龍樹の中観思想に近い。さらに、道元によって日本にもたらされた曹洞禅は、臨済禅の公案という文字さえ原則として用いない黙照禅であり、釈尊直説すなわち人間ブッダの教えに最も忠実な宗派であるといえるであろう。
(まとめ)
禅とは、以下の3点を核心とする生活実践であり、公案を解くには不可欠の視点である。
1 禅には己事究明(自分の正体は何か)以外の問題はない
2 意識現象(見えたまま、感じたまま)以外に真実はない(真実は常に現前している)
3 思考(分析・識別)を加えた時点で既に間違っている